こんにちは。あいうえです。
今日も、ちょっと役立つお話をお届けします。
今回は、『東大生が日本を100人の島に例えたら面白いほど経済がわかった!』(ムギタロー著)のお話です。

本記事にはアフィリエイト広告を含みます。リンクから商品を購入いただくと、運営者に報酬が入る場合がありますが、紹介内容は筆者が実際に読んだり体験したものをもとにしています。
はじめに
私は経済についてきちんと学んだのは中学生のときの公民や、受験対策での現代社会くらいでした。 社会人になってからは、新聞やネットニュースなどを読むことで得られた知識が大半です。
最近では、YouTubeで政治や経済をわかりやすく解説してくれる動画も増えてきました。でも、私はどちらかというと文章でじっくり読む方が頭に入りやすいので本を探していました。
今回読んだのは『東大生が日本を100人の島に例えたら面白いほど経済がわかった!』(ムギタロー著)という本。 表紙に描かれた動物のイラストがなんとも可愛らしくて、「これはとっつきやすそう!」です。タイトルにもある「100人の島」という設定も、ある程度シンプルにして考えた方が理解しやすいだろうと思い、選んでみました。
本の印象|みんなが幸せに生きるために
この本から受けた印象として、「みんながよりよく生きていくためには、どう考えるべきか」を問いかけているように感じました。 そのためには、社会のしくみを理解することが大切だという著者の考えが読み取れます。 これは本の最後の「おわりに」の部分にもまとめられています。
また、物事を二つに分けて考えるのではなく、テレビの音量のように0〜100の間で調整するような考え方が必要だという点も印象的でした。 たとえば、資本主義と社会主義のそれぞれの良い部分をうまく組み合わせていくという考え方です。
読んでわかったこと|税金は集めるためが目的でなく、調整のため
この本を通じて理解できたことは、国は税金を集めてから支出しているのではなく、必要に応じてお金を発行し、そのうえで税を通じて経済を調整している、という点です。 つまり、現在の税の役割は「通貨に価値を持たせる」「望ましい経済状況を促す/望ましくない状況を抑制する」ことにある、という考え方が示されていました。
そのため、「公務員が税金で食べている」とか「高額納税者を優遇しろ」といった見方は真ではありません。
また、国にとって本当に必要なのは、通貨としての日本円そのものではなく、国民が生み出す食料・モノ・サービスといった実体である、ということも印象的でした。たとえ日本円が一時的に使えなくなったとしても、そうした実体があれば生活は続けられる——混乱はあるかもしれませんが、新しい通貨が機能すれば、それでも国は成り立っていく、という見方です。
さらに、よく財政赤字の話で引き合いに出される「ギリシャ危機」についても、日本とは状況が異なることが指摘されていました。 ギリシャはユーロ圏にあり、自国で通貨を発行できなかったため、国債の買い取りができず、結果として支払い不能に陥りました。 一方、日本は自国通貨である円を自ら発行できるため、同じような危機には直結しない、という説明がされています。
まとめ
この本は、全体的に整理されていて読みやすく、「みんなが幸せに生きるためにはどう考えればよいか」という視点に立って書かれている印象を受けました。 新聞やニュースで取り上げられる経済の話題も、これを読んでおくと少し見え方が変わってくるかもしれません。
著者は理系(工学部)出身ということもあり、論理的でわかりやすい構成です。 私自身も理系出身ですが、同じような方にとっては特にとっつきやすく感じられるのではないかと思います。 経済にあまり触れる機会がない方も、一度この本を通して考えてみることで、基本的な理解のきっかけになるのではないでしょうか。
本記事にはアフィリエイト広告を含みます。リンクから商品を購入いただくと、運営者に報酬が入る場合がありますが、紹介内容は筆者が実際に読んだり体験したものをもとにしています。
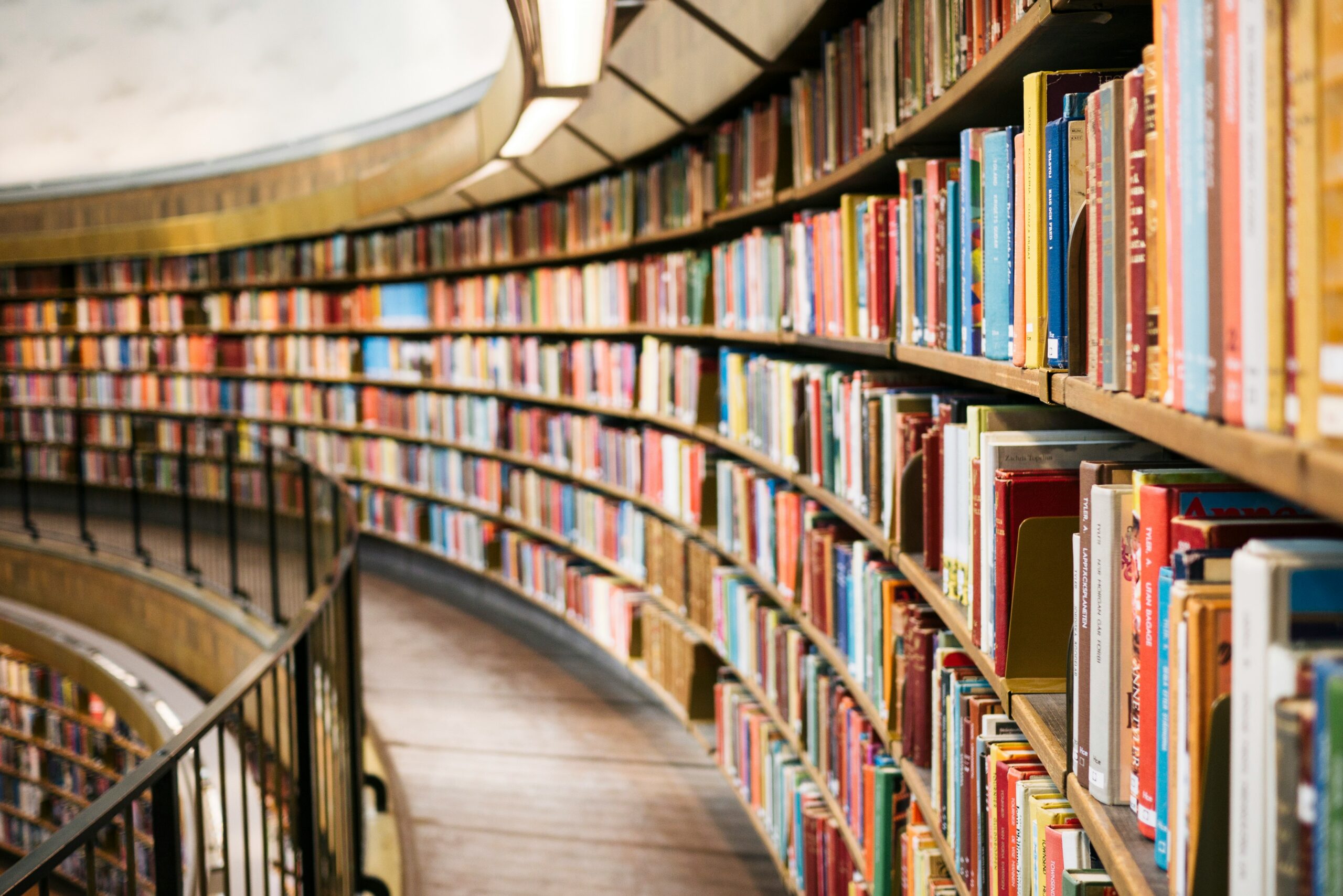


コメント