こんにちは。あいうえです。
今日も、ちょっと役立つお話をお届けします。
今回は、『小学生の勉強は習慣が9割 自分から机に向かえる子になる科学的に正しいメソッド』(菊池洋匡 著)のお話です。

本記事にはアフィリエイト広告を含みます。リンクから商品を購入いただくと、運営者に報酬が入る場合がありますが、紹介内容は筆者が実際に読んだり体験したものをもとにしています。
はじめに
前回、「続ける思考」で習慣化のコツなどを学びました。
でも1冊だけでは、その方法が自分にあっているのかどうか、他にも方法はないのかと考えてしまいます。
そこで小学生の勉強での「習慣」を教えるこの本を選びました。
この本は、子どもを持つ親だけでなく、大人にも読んでほしい内容になっています。 テーマは「習慣化」。自分の行動をコントロールし、繰り返すことで良い習慣につなげる方法が紹介されています。
自己コントロールの力は、学力や社会的な成功、人間関係の土台にもなる大切なものです。本書では「どうすれば良い行動を習慣化できるか」が具体的に解説されており、日常生活に取り入れやすい工夫が多く紹介されています。
習慣が身につけば、歯磨きのように自然に続けられるようになり、ストレスなく行動を継続できるのが魅力です。
どうやって習慣化する?
行動を習慣化するには、小さな目標(スモールゴール)を設定してハードルを下げることが大切です。 例えば「本を5分だけ読む」「それも難しければ3分だけ読む」といった具合に、できる範囲で始めるのが効果的です。
私自身も実際に試しましたが、短い時間から取りかかることで意外と集中でき、結果的にしっかり読めました。 まずは「取りかかること」自体が習慣化の第一歩になります。
ハードルを下げることは「続ける思考」にも書いてありました。習慣化には非常に大切なことのようです。
頑張らないでよい仕組み
また、「頑張る」だけでは長続きしません。 「頑張る=普通でないこと」という感覚もあるため、日常的に無理なく続けられる仕組みづくりが必要です。
私も、「頑張る」と逆に「続かない」と感じることが多くあります。だからこそ、頑張らなくてもできる範囲で生活習慣を整えることが大切だと思っています。
結果目標を行動目標に落とし込むことが大切
結果目標は「次の試験で90点取る」のようなものですが、行動目標は「ドリルをやる」といった形になります。 ただし、行動目標はそれだけでは不十分です。「具体的」で「計測できる」ものにする必要があります。
また、行動目標は「○○しない」ではなく「○○する」といった肯定的な行動を表す形で設定したほうが良いとされています。
かきくけこ
勉強(ほかの仕事も同様ですが)では、効率的に進めるために適切なレベルの負荷が必要とされています。 そのときに役立つのが「かきくけこ」という考え方です。
大人でもSMARTルール(Specific:具体的、Measurable:計測できる、Achievable:達成できる、Relevant:関連性がある、Time-bound:期限がある)が知られていますが、それを子ども向けにわかりやすくしたものが「かきくけこ」です。
- か(関連性がある) 何のために行うのか理由があることが大切です。
- き(期限がある) やりたいけれど手がつかないということを避けるために、期限を設定する必要があります。期限があることで、完遂した、できなかったという実感にもつながります。
- く(具体的) 何をするのか分からないと行動に移しにくいため、ドリルを1ページ解く、本を1ページ読むといった具体性が必要です。
- け(計測できる) 数値で測定できないと「できた」「できない」が曖昧になります。達成や評価の目安には数値化が必要です。
- こ(これならできる) あまりに大きすぎる目標は無理だと感じてしまいます。料理をいきなりたくさん作ると途中でやめたくなるのと同じで、無理のない範囲に設定することが大切です。
この「かきくけこ」は、大人にとっても分かりやすく、SMARTルールよりも直感的に伝わる点があると考えられています。
if-thenプランニング
行動を起こすには「やる気スイッチ」を入れる方法が必要です。その一つが if-thenプランニング です。
if-thenプランニングとは、「○○になったら□□する」という形で条件と行動を結びつけておく方法です。 ペンシルベニア大学とコロンビア・ビジネス・スクールの共同研究では、この方法を用いることで高校生の夏休み中の勉強量が2倍以上に増えたという報告があります。
例えば「木曜日の17時になったら、算数プリントをする」といった具合です。 さらに「木曜日の17時になったら、自室から算数のテキストとノートを持ってきて、リビングで算数の宿題を始める。図や式を丁寧に書き込みながら取り組む」といったように、状況をより具体的に決めておくとスムーズに勉強を始められるとされています。
この方法は勉強だけでなく、服を選ぶときなど日常の意思決定にも応用できます。 著名な会社のCEOなどは、日常で着る服を固定していることが多いといわれています。実際に私もある程度服装については変化がないようにしています。服装を固定することで確かに楽になりました。おしゃれかと言われるとそうではないかもしれませんが。
このようにあらかじめ決めておくことで、勉強や生活における余計な意思決定を減らし、行動にすぐ移れるようになります。勉強自体にも集中しやすくなるのがメリットです。
まとめ
この本は、習慣化や習慣づけをテーマにしたものです。 「続ける思考」にも書かれていたように、スモールゴールを設定して小さく始めることは重要です。
また、「頑張り」は長く続かないため、習慣化が必要だという点も大切なポイントです。
具体的な方法としては、「かきくけこ」や「if-thenプランニング」などを活用していくことが挙げられます。これらの方法は非常に有効であり、大人にとっても役立ちます。
これまで習慣化がうまくいかなかった方、多くの人にとって参考になる内容です。もし「続ける思考」を読んでさらにもう一冊取り入れるとすれば、この本をおすすめします。
詳細はぜひ実際に読んでみてください。
本記事にはアフィリエイト広告を含みます。リンクから商品を購入いただくと、運営者に報酬が入る場合がありますが、紹介内容は筆者が実際に読んだり体験したものをもとにしています。
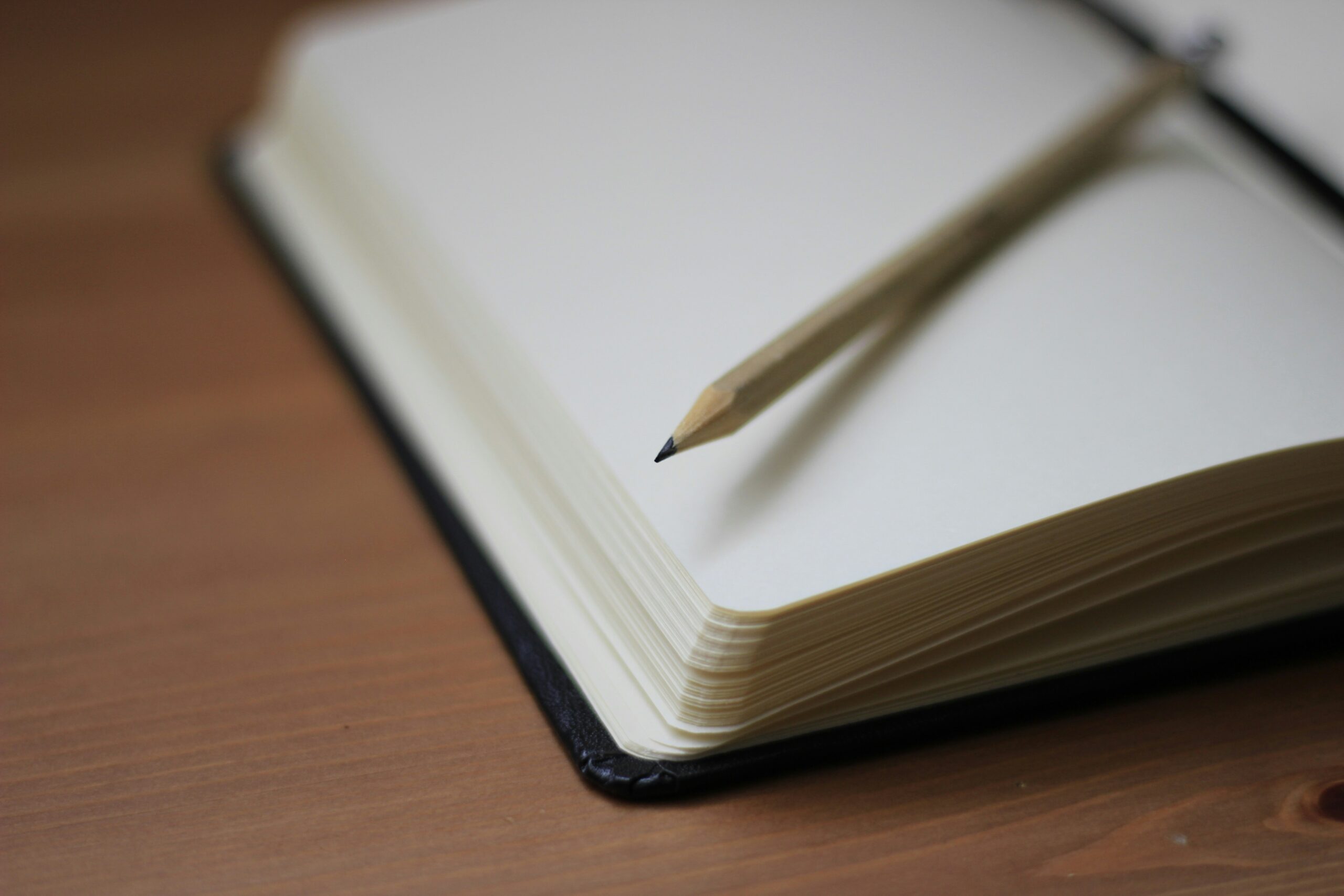


コメント