こんにちは。
あいうえです。 今日も、ちょっと役立つお話をお届けします。
今回は『イシューからはじめよ』(安宅和人 著)という本についてのお話です。

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。リンク先の商品を購入すると、運営者に収益が発生する場合があります。
はじめに
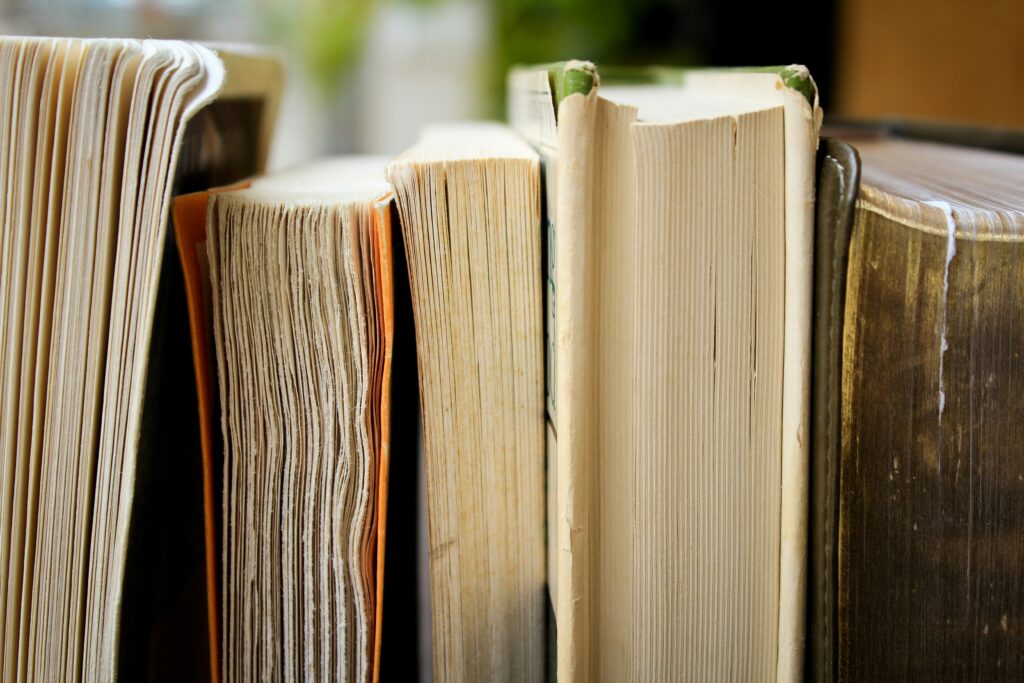
マーケティングの本が続いたので、今回はジャンルを変えてみようと思いました。 現在の仕事にもある程度通じる「知的生産」に関する本です。
そういえば、改めて“考え方”を学ぶことって、なかなかなかったような…(忘れてしまっているだけかもしれませんが)。
今回は、知的生産に関する名著――『イシューからはじめよ』(安宅和人 著)についてご紹介します。
イシューとは何か?

本書では、一貫して「イシュー」に焦点を当てています。
「意味あるアウトプットを、一定期間内に生み出す必要のある人」にとって、本当に考えるべきことは何か――その問いかけから始まる導入は、非常に引き込まれます。
最近では、MECE(ミーシー)やフレームワークといったツールが、ロジカル・シンキングの文脈でよく登場しますが、著者はこうしたものを「あくまでツールに過ぎない」と述べます。
どれだけツールを駆使しても、「本質的に重要な問題(=イシュー)」を捉えていなければ意味がない。
では、イシューとは何か?
“イシュー(issue)”とは、一般に「問題」「課題」「論点」「懸案事項」と訳されますが、本書では以下のように定義されています。
イシューとは、以下の2条件を同時に満たすもの:
- A)複数の集団の間で決着がついていない問題
- B)根本に関わる、もしくは白黒がはっきりしていない問題
イシューをどう設定するか?
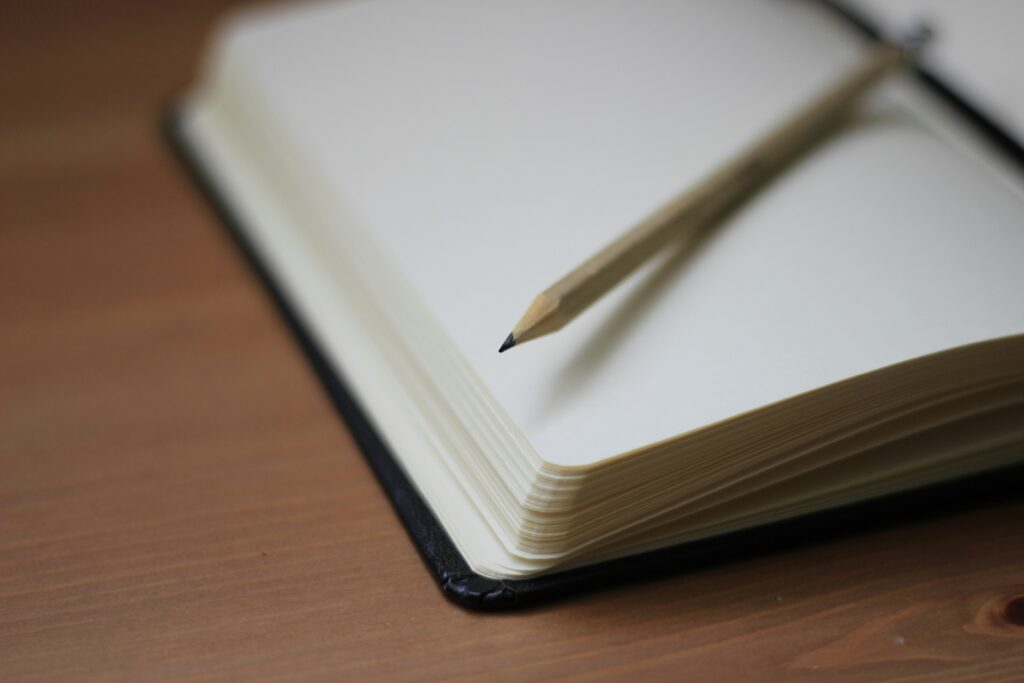
では、イシューはどう設定すればよいのでしょうか? 本書では、「見極める力」と「仮説を立てる力」の重要性が強調されています。
特に、仮説を立てることの重要性について、以下の3点が挙げられます。
仮説を立てることが重要な3つの理由:
- 仮説がなければ、答えを出しうるレベルのイシューにできない
- 「何に答えを出そうとしているか」が明確になり、必要な情報や分析対象が定まる
- 出てきた分析結果に対する解釈が明確になる
要するに、「何に対して解を出すのか」を明確にすることで、結果のブレや曖昧さを減らすということです。納得感があります。
イシューを言葉にして表現する

「最終的に何を言いたいのか」は、言葉にして初めて明確になる―― この考え方にも深く共感しました。
図やイメージも大切ですが、言葉にできなければ本質があやふやなまま。輪郭がぼやけてしまいます。 本書では、イシューを言語化する際のポイントも紹介されています。
イシュー表現のポイント:
- Where / What / How の形式を意識する
- 比較表現を取り入れることで、明確さが増す
無駄のない、すぐれた名著
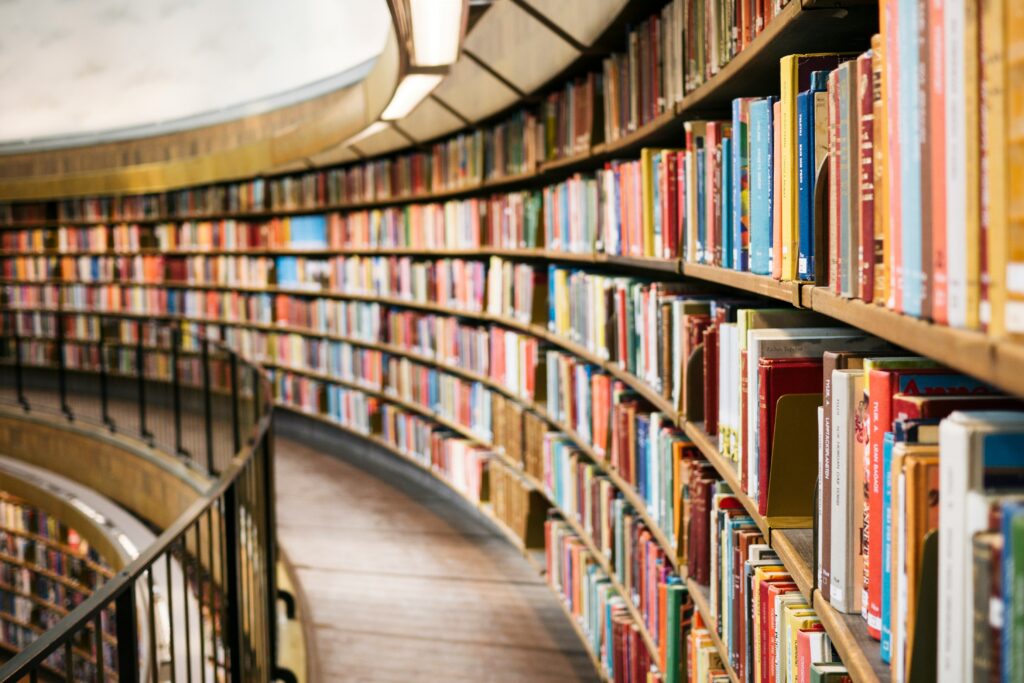
本書はこのあと、分析方法やストーリーラインの組み立てにも進みますが、やはりすべての出発点は「イシュー設定」です。
知的生産の方法論を学びたい人には、間違いなくおすすめできる一冊です。
内容は非常に練られており、無駄がまったくありません。
読解には集中力が必要で、「わからないな」と思ったらページを戻って読み直し、メモを取りながら進めるのが合うタイプの本です。
気軽にゴロゴロしながら読むには少し硬派かもしれませんが、コラムや章ごとに登場する科学者の言葉にも大きな学びがあります。
まとめ
非常に良い本です。無駄がなく、本質にまっすぐ迫ってくる印象があります。
高校生や大学生(文理問わず)はもちろん、仕事の質を上げたいビジネスパーソンにも強くおすすめできます。
個人的には「もっと早く出会いたかった」と思える一冊。 今後も何度も読み返すことになると思います。
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。リンク先の商品を購入すると、運営者に収益が発生する場合があります。



コメント