こんにちは。あいうえです。
今日も、ちょっと役立つお話をお届けします。
今回は『新しい文章力の教室 苦手を得意に変えるナタリー式トレーニング』(唐木元 著)という本についてのお話です。

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。リンク先の商品を購入すると、運営者に収益が発生する場合があります。
はじめに|文章って、やっぱり難しい?
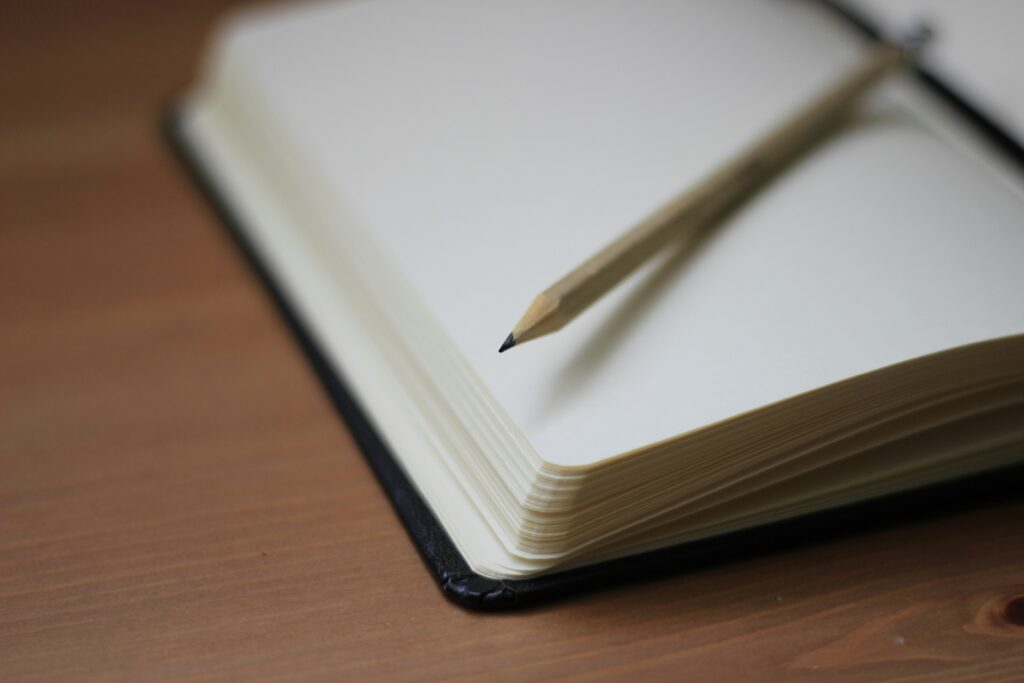
「文章を書くのって、なんだか難しい」 そう感じたことはありませんか?
私は、昔から読書感想文が大の苦手でした。 いざ書こうとしても、「何をどう書いたらいいのか」がまったくわからず、時間だけが過ぎていく…。そんなことを何度も経験してきました。
それでも仕事では、ある程度の経験を積むうちに、文章を早く書けるようになってきました。 おそらく「型」のようなものが自然と身についてきたからだと思います。
では、ブログ記事にも「型」はあるのでしょうか? 「もっと効率よく、読みやすく書くためのヒントがほしい」――そんな思いから、今回手に取ったのが、『新しい文章力の教室』という本です。
この本を通じて、「伝わる文章とはどんなものか?」「そのために何をどう意識すればよいのか?」を、あらためて学んでみたいと思います。
「良い文章」とは?|“完読”されることがゴール
では、そもそも「良い文章」とは、どんな文章なのでしょうか?
『新しい文章力の教室』では、それを―― 「完読される文章」 と定義しています。
つまり、「最後まで読んでもらえる文章」のことです。
たとえ文体が美しくても、読み手に内容が伝わらなかったり、途中で読むのをやめられてしまったりしたら、それは“良い文章”とは言えません。
大切なのは、「情報を不足なく、かつ分かりやすく相手に手渡しすること」。 その結果、書き手のメッセージがきちんと読み手に届く――そこに文章の本当の役割があります。
どれだけ情報が詰め込まれていても、読者が途中で離脱してしまっては意味がないのです。
「良い文章」とは、「最後まで読んでもらえる、伝わる文章」。 このシンプルな定義を出発点として、本書では具体的な書き方が紹介されていきます。
書き始める前に必要なのは、「主眼」と「骨子」と下準備
文章を書こうとするとき、つい勢いで書き始めてしまう―― そんな経験はありませんか?私も何度もあります。
でも、「何をどう書くか」がぼんやりしたままだと、書いているうちに話が迷子になってしまいます。
本書では、「書く前に必ず「主眼」と「骨子」を立てるべき」だと繰り返し述べられています。
「主眼」とは、文章全体を通して伝えたいメッセージやテーマのこと。 「骨子」は、その主眼を伝えるための構成=道筋のことです。
そして、この骨子は次の3つの要素から構成されます:
- 要素(何を話すか)
- 順番(どれから話すか)
- 軽重(どのくらい詳しく話すか)
つまり、「どんな内容を」「どの順番で」「どの程度の深さで」伝えるかを決めておくこと。 この設計図があることで、文章は読みやすくなり、最後まで読んでもらえる可能性が高くなります。
加えて、著者は「いきなり書き始めてはいけない」と注意しています。 構成の見通しをきちんと立てたうえで、書き始める準備を整えることが大切だと述べています。
そのために使えるのが、本書で紹介されている「構造シート」です。 これは、主眼と骨子を視覚的に整理して、文章の全体像をあらかじめ把握するために作成します。
著者は、この構造シートを「最初は手書きで行う」ことを推奨しています。 紙に書き出すことで、思考が整理され、自然と構成が固まっていくのです。
この考え方は、以前紹介した『アウトプット大全』(樺沢紫苑著)にも共通していました。 同書でも、アイデア出しは「アナログ=紙とペン」で行うのが効果的だと述べられていました。
悩まずに書くために――文章も「プラモデル化」する
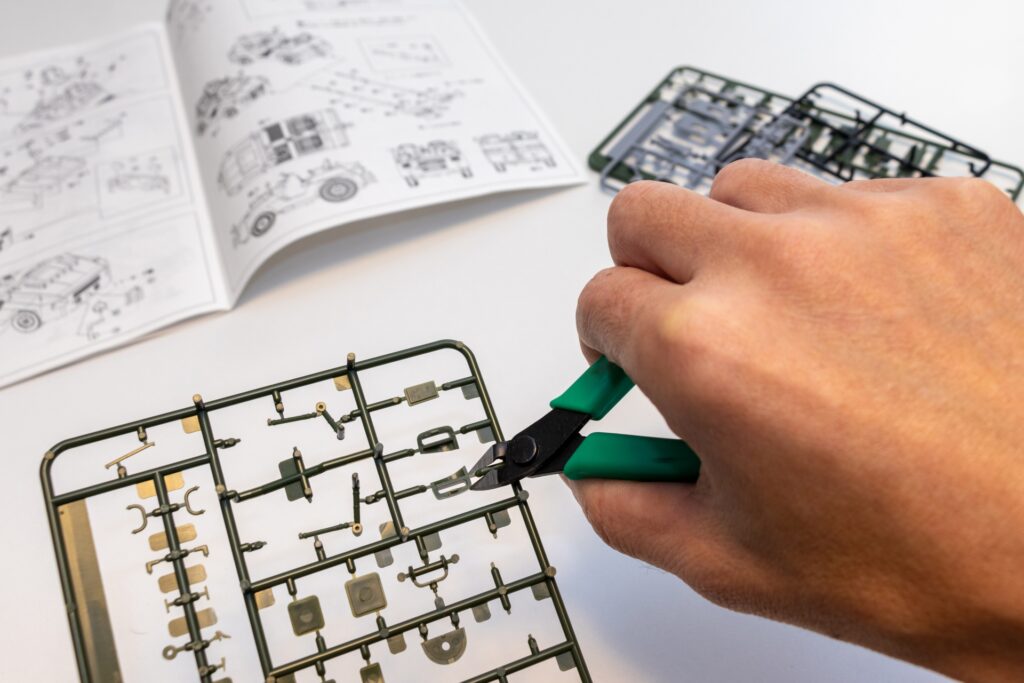
文章を書いていて、手が止まってしまう瞬間。 「あれ、何をどう書くんだっけ?」と迷ってしまうこと、ありませんか?
本書では、そんなときのために―― 「作文をプラモデル化しておこう」という考え方が紹介されています。
プラモデルは、
- パーツ(部品)
- 取扱説明書(組み立て手順)
- 箱絵(完成イメージ) この3つがそろってはじめて、1つの「完成形」を目指して組み立てることができますよね。
これを文章に当てはめると、次のようになります:
- 箱絵(完成イメージ)=主眼 → どんなことを伝えたい文章なのか。最終的なイメージをはっきりさせる。
- パーツ=要素 → 何を言いたいか。話すべきトピックをあらかじめ洗い出しておく。
- 取扱説明書=順番・軽重 → どれから話すか、どの部分を詳しく伝えるか。構成の優先順位を決めておく。
つまり、「作文のプラモデル」をあらかじめ設計しておけば、いざ書くときに悩まず進めるというわけです。
この考え方は、ビジネスでよく言われる「仕組み化」や「フレームワーク思考」にも通じます。
まとめ|文章は“感覚”だけでなく、技術でもよくなる
本書『新しい文章力の教室』は、タイトル通り、“新しい視点”で文章を書く力を鍛えてくれる一冊でした。
とくに印象的だったのは、第1章に集約された「肝の部分」です。 ここでは「主眼」や「骨子」といった、文章を構成するための根本的な考え方が示されていて、まさにこの本の軸といえる内容でした。
その後の章では、語尾の使い方や接続語、文末表現など、言葉の細部にわたる実践的な工夫が丁寧に解説されています。
特に面白かったのは、感覚的に「これがよさそう」と使っていた書き方に対して、 「なぜそれが良いのか」を言語化して説明してくれている点です。 漠然とした感覚を“技術”として捉え直せることで、文章の「再現性」が格段に上がると感じました。
また、仕上げとして紹介されていた「黙読→音読して語呂を確かめる」という方法は、私にとって新鮮でした。
すぐに取り入れられる工夫でもあります。
「文章をつくる」とは、やっぱり丁寧な作業だ
本書を通してあらためて感じたのは、 文章をつくるというのは、やっぱり丁寧にやるしかないということ。
その丁寧なプロセスをどう積み上げていくか――その方法が、この本にはしっかり書かれています。 テクニック本というより、実務に根ざした文章の指南書という印象です。
こんな方におすすめ
本書は、次のような方に特におすすめです:
- これからSNSやブログで情報発信を始めようとしている方
- すでに文章を書いているけれど、もっと伝わる書き方を学びたい方
- 自分の文章を見直し、新しい視点や技術を取り入れたい方
初心者だけでなく、ある程度書き慣れた人にも気づきの多い一冊だと思います。
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。リンク先の商品を購入すると、運営者に収益が発生する場合があります。
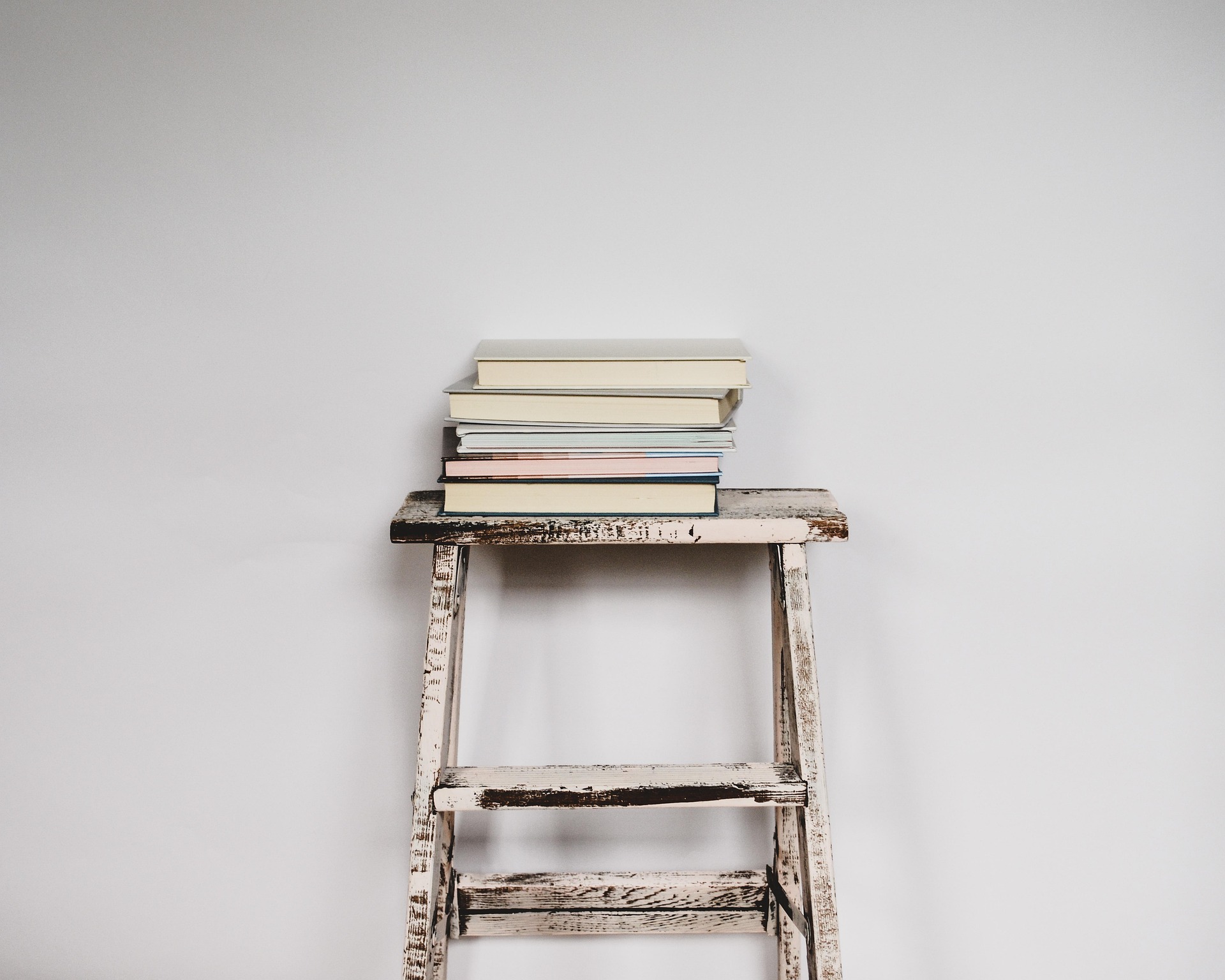


コメント