こんにちは。あいうえです。
今日も、ちょっと役立つお話をお届けします。
今回は『学びを結果に変えるアウトプット大全』(樺沢紫苑 著)という本についてのお話です。

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。リンク先の商品を購入すると、運営者に収益が発生する場合があります。
はじめに|アウトプットについて考えはじめたきっかけ
最近、ブログというアウトプットを続けています。 書くこと自体は嫌いではなく、取り組んでいておもしろみも感じています。 でも、いざ自分で続けてみると、「見るのとやるのとではずいぶん違うものだな」と思わされることが増えてきました。
ちょうどその頃、なんとなくインプットばかりに偏っていて、「学んでいるつもりなのに、身についている実感が薄い」と感じるようになっていました。 そんなときに気になったのが、「アウトプットを前提にすることの大切さ」という言葉でした。
アウトプットについて、もう少しきちんと考えてみたい。 そんな思いから手に取ったのが、『学びを結果に変えるアウトプット大全』(樺沢紫苑 著)という本です。
著者の樺沢さんは精神科医として活動されながら、 作家、インフルエンサーとしても知られている方です。
冒頭には、ご自身の生活スタイルについても触れられていて、
- 月10本以上の映画鑑賞
- 月20冊以上の読書
- 週に4〜5回のジム通い
- 月10回以上の飲み会
- 年30日以上の海外旅行
といった、非常に充実した日々を送っている様子が紹介されています。 仕事との両立を考えると、とても真似できそうにないように思えますが、その背景には「インプットとアウトプットのバランスを工夫し、学びと成長のスピードを最大化してきたこと」があるのだそうです。
「バランスを工夫するだけで、時間の使い方や成果が大きく変わる」という発想は、自分にとって新鮮でした。 もし、そんな方法があるのなら、自分でも取り入れてみたい。 そう思いながら、本書を読み進めてみました。
今回は、そんな『アウトプット大全』について、 私自身の実感を交えながら、紹介してみたいと思います。
アウトプットの基本法則|学びが“成果”に変わる仕組み
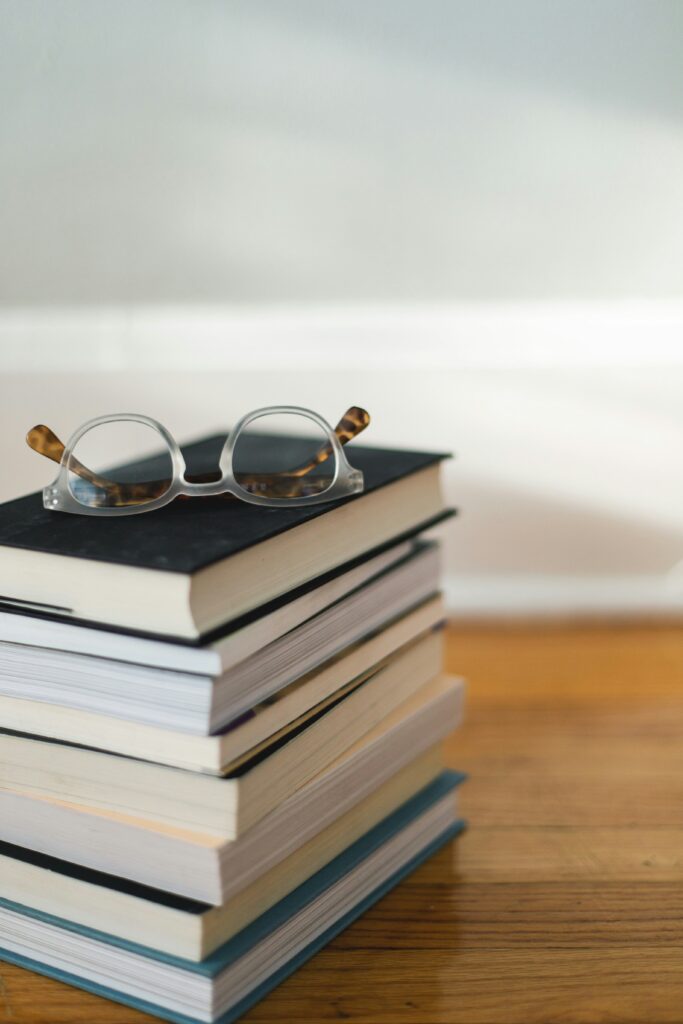
本書では、アウトプットを「学びや成長を現実の変化につなげるための核心」だと位置づけています。 その根底には、「インプットとアウトプットの反復こそが知的生産活動の軸である」という考え方があります。
学びというのは、一度取り入れて終わりではなく、 「取り入れたことを実際に使ってみる(アウトプット)」ことで定着し、 そこから気づきを得て、次のインプットへとつながっていきます。
このサイクルを何度も回していくことで、 一段一段、少しずつ成長していける―― 本書ではこれを「成長の螺旋階段の法則」と表現しています。
もうひとつ印象的だったのは、 「現実はアウトプットによってしか変わらない」という指摘です。
アウトプットとは、たとえば
- 話す
- 書く
- 行動する
といった、“自分の中から外に出す行為”のこと。 それに対して、インプットとは
- 読む
- 聞く
といった、“情報を取り込む行為”を指します。
自己成長の観点では、つい「インプットの量」に目が行きがちですが、本書では一貫して「アウトプットの量こそが成長を決める」と説かれています。
インプットとアウトプットの黄金比率
印象に残ったのは、「インプットとアウトプットの黄金比」として紹介されていた【3:7】というバランスです。
多くの人は、読書や学習に多くの時間を使い、アウトプットの時間が圧倒的に少ないままです。 けれど、たとえば1か月に3冊読む人よりも、 1冊をじっくり読んで、それについて何かしらのアウトプット(感想を書く、人に話す)をした人のほうが、成長の実感を得やすい――というのが著者の主張です。
また、アウトプットした結果をそのままにせず、
- なぜうまくいったのか
- なぜうまくいかなかったのか
- 次は何をすればいいのか
という「フィードバック」の視点も重要だとしています。 インプット → アウトプット → フィードバックという流れが、より深い学びを生むと感じました。
このように、アウトプットは「知識を活かす行為」であるだけでなく、 自分自身の変化や成長、そしてその先にある成果までも導くための行動だということがよくわかりました。
印象に残ったアウトプットの方法|構成と作業を分けるスライドづくり
本書のなかで、特に印象に残った具体的な方法のひとつが、著者が行っているプレゼン用スライドの作成手順についての話でした。
筆者は、90分のプレゼン用スライドを2日間で完成させるそうです。それだけの分量を短期間で仕上げられることに、最初は驚きました。
その背景には、「構成を考えること」と「作業として手を動かすこと」を分けるという、シンプルながらも効率的な工夫があります。
1. ノートでアイデアを出す(アナログ作業)
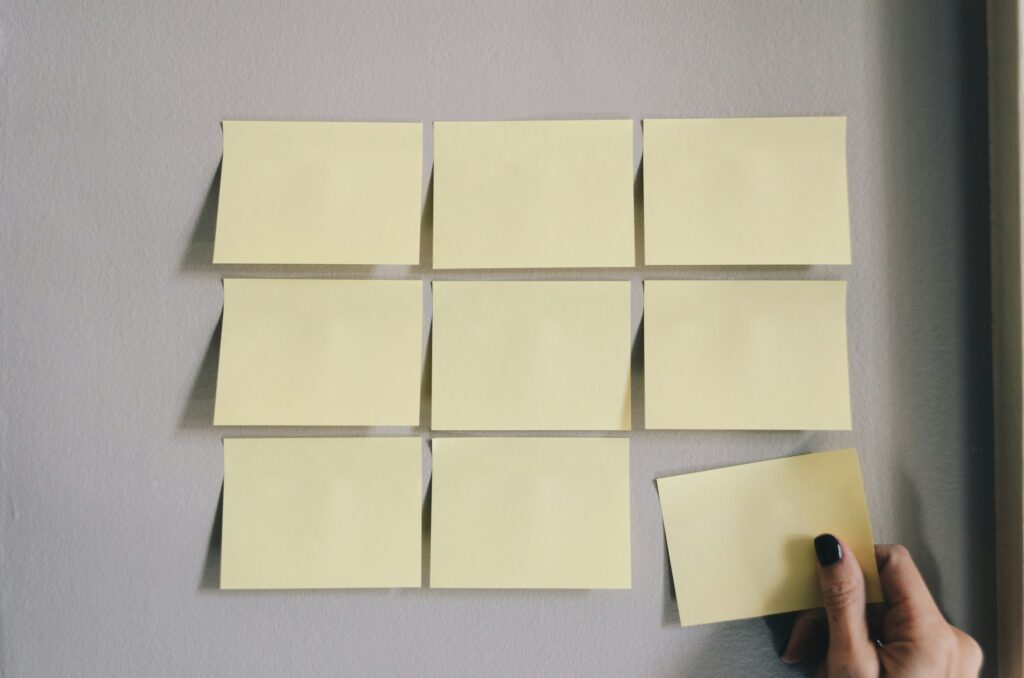
まず最初に行うのは、ノートを使ったアイデア出しです。 著者は、本書全体を通じて「アイデア出しはアナログで行うのがよい」と繰り返し述べています。 ペンとノート(あるいはカード)で手を動かしながら考えることで、思いがけないアイデアが浮かんでくることがあるそうです。
具体的には、A4ノートの見開きを4分割して使います。 時計の文字盤をイメージしながら、右上→右下→左下→左上の順に、次のように書いていきます:
- 右上:イントロダクション(導入)
- 右下:入門的な話
- 左下:応用的な話
- 左上:まとめ・結論
この4分割構成は、プレゼンだけでなく、ブログや資料づくりにも応用できそうだと感じました。
2. アウトラインで全体構成を決める
次に行うのが、Wordのアウトライン機能を使った構成づくりです。
見出しを階層的に並べながら、プレゼンの全体像を整理していきます。 ここで著者が述べていたのが、「90分の講義なら90行、1行=スライド1枚=1分」というルールです。 この考え方に沿えば、スライド枚数と時間配分が自然と一致するため、無理なく話を組み立てることができます。
また、アウトライン機能を使うことで、構成を手早く整理できるようになり、 全体にかかる時間を半分以下に短縮できるとも述べられていました。
3. PowerPointでスライドをつくる(作業モード)
構成が固まったあとは、PowerPointを使ってスライドを作成していきます。 この段階は、構成という“考える作業”はすでに終わっているので、 あとはアウトラインに沿って、手を動かすだけの“運動作業”になるのだそうです。
このように、「構成を練る工程」と「スライドを作る工程」を明確に分けることで、 効率よく、ぶれのない資料が作れるということがよくわかりました。
この方法自体はプレゼン用の手法ではありますが、 文章を書くときやブログ記事の構成を練るときにも応用できる考え方だと感じました。 「まず全体を設計してから、手を動かす」 そうした意識を持つことで、無駄なくアウトプットを形にできるのではないかと思います。
まとめ|変えたいのなら、アウトプットから始めてみる
この本を通して一貫して語られているのは、 「アウトプットしないことには、現実は変わらない」というメッセージです。
インプットだけでも、たしかに頭の中の世界――つまり「脳内世界」は変わります。 けれど、現実が変わるのは、それを外に出し、行動したときだけです。 このことは、実は本の最初の数ページに、はっきりと書かれていました。
「行動しなければ、何も変わらない」
たとえば行動には、SNSでの発信やブログを書くことも含まれます。 それだけでなく、日常の中で「誰かをほめる」「叱る」といったこともまた、アウトプットのひとつです。
とはいえ、本書の目的は「ただ行動すればいい」という話ではありません。 タイトルにもあるとおり、“アウトプットで結果を出す”ための方法を、非常に具体的に示しているところが、この本の大きな特長です。
著者自身の体験やエピソードをもとに、アウトプットの方法や工夫が全80項目にわたって紹介されており、どれも1項目につき見開き2~4ページほどで読みやすくまとめられています。図やイラストも多く、気軽に手に取りやすい構成です。
「最近、なにか行き詰まりを感じている」 「努力しているのに、結果がついてこない」
もしそんな感覚があるとしたら、それはアウトプットの量や方法が少し足りていないのかもしれません。
少し視点を変えて、行動の仕方を工夫してみる。 それだけで、現実の見え方が変わってくることもある―― そんな可能性を感じさせてくれる一冊でした。
なお、本書には漫画版も出版されているようです。
ストーリー仕立てで構成されているとのことで、もしもっと手軽に読みたいという方には、そちらも選択肢の一つかもしれません(私は未読です)。
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。リンク先の商品を購入すると、運営者に収益が発生する場合があります。



コメント