こんにちは。あいうえです。
今日も、ちょっと役立つお話をお届けします。
今回は『指導歴25年超&“生の声”で実証! [中学生]成績トップの子の親がしていること』(國立拓治 著)という本についてのお話です。

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。リンク先の商品を購入すると、運営者に収益が発生する場合があります。
はじめに
今回は、教育に関する一冊――『成績トップの子の親がしていること』を取り上げます。
この本は、知り合いに勧められて購入したものです。 自分自身の子ども時代とは環境が大きく変わっている中で、どのように子どもと向き合えばよいか悩んでいたタイミングでもあり、ヒントを得られそうだと感じました。
まずは“目次チェック”から
読み始める前に、まずは目次をチェックしてみることにしました。 これは以前読んだ『コンサル時代に教わった 仕事ができる人の当たり前』(西原亮著)の中で紹介されていた方法です。
目次からも、気になるポイントがいくつか見えてきました。 たとえば、「スマホとの付き合い方」や「ながら勉強の是非」といった、現代ならではのテーマが目につきます。 また、「休日も起床時間はブレない」といった生活リズムへのこだわりや、「勉強に対するご褒美」の扱いについても触れられているようです。
成績優秀な子どもの家庭では、どんなスタンスで日常を送っているのか―― その“答え”が、この本には書かれていそうです。
「目を離さず、手は出さず」──理想の親子の距離感とは?
本書では、成績上位の子どもを育てる親に共通するスタンスとして、 「目を離さず、手は出さず」という距離感が大切であるとされています。
その具体的な実践例として、子どものテスト結果や通知表の内容をきちんと把握しておくことが挙げられていました。 単に点数だけでなく、平均点やテスト全体の順位なども含めて、全体の位置づけを確認することがポイントのようです。
これらの情報を継続的に記録・管理するには、表計算ソフトを使って一覧にしておくのも有効だと感じました。 数値としての推移が見えることで、親も過度に介入せずに、必要なサポートを見極めやすくなるはずです。
たとえるなら、つかず離れずの“ショップ店員”のような距離感。 必要なときにはサッと手を差し伸べるけれど、普段はそっと見守っている―― そんな関わり方が、子どもにとっても心地よく、自立を促すのだと感じました。
スマホとの付き合い方|「自室に入れない」が基本ルール
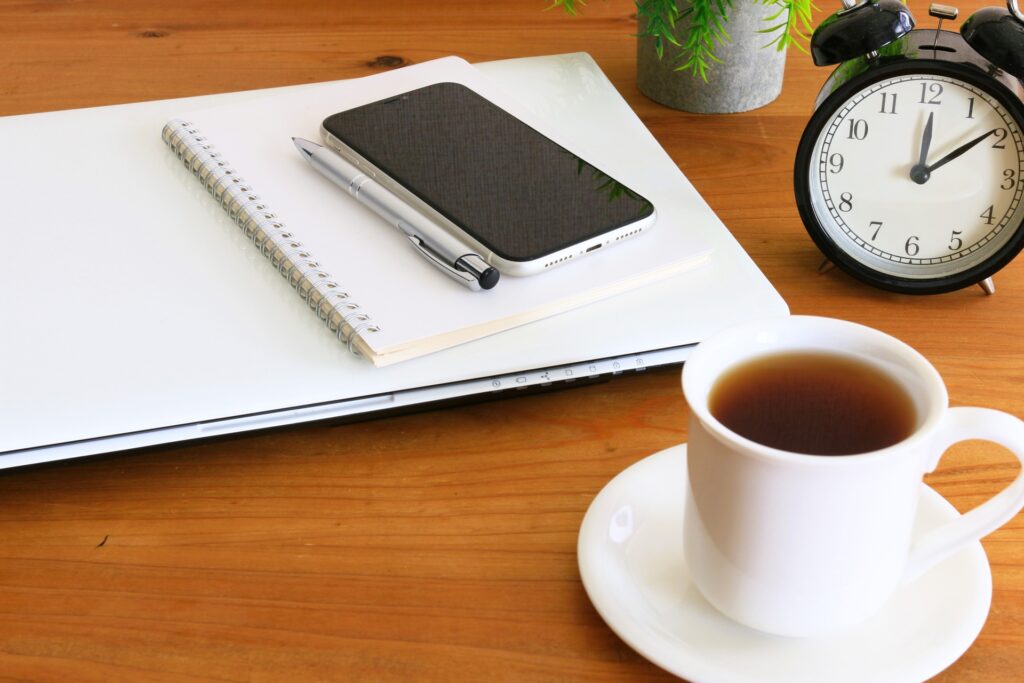
スマートフォンとの付き合い方は、どの家庭でも頭を悩ませるテーマではないでしょうか。 私自身の家庭でも、その影響力の大きさを考えて、いくつかのルールを決めています。
たとえば――
- スマホの使用は午後8時30分まで
- 使用するのは1階のみ
このようなルールを設けて、使う時間や場所を制限するようにしています。
本書でも、スマホへの対応は極めて重要視されていました。 とくに印象的だったのは、「自室には絶対にスマホを入れない」という考え方。 これは、勉強していない時間であっても同様で、つまり“プライベートな空間にすらスマホは持ち込ませない”という姿勢です。 さらに「寝室にもスマホは入れない」と、徹底したルールが推奨されていました。
また、スマホを手に取っていなくても、近くにあるだけで集中力が下がるという海外(アメリカ)の調査結果にも触れられており、 単なるデジタル機器ではなく、“学習環境に影響を与える要因”として捉える重要性が語られていました。
「ながら勉強」はNG──集中力を奪うマルチタスクの落とし穴

本書では、テレビやYouTubeなどを見つつ勉強しないと81.4%の家庭が回答しているとのことでした。
これは、マルチタスク状態になることで、集中力が低下してしまうためだと考えられます。 一見、音を流しているだけ・目線を外していないだけ…と思ってしまいがちですが、脳の処理は確実に分散されてしまいます。
こうしたマルチタスクの弊害については、『アウトプット大全』(樺沢紫苑著)の中でも触れられており、 学習効率を下げる大きな要因の一つとして注意喚起されていました。
生活リズムと学力の関係
本書では、起床時間は休日であっても基本的にブレないことが重要だと述べられていました。
そして、キーワードとして何度も登場するのが、「早寝・早起き・朝ご飯」。 これは単なる健康習慣ではなく、学力向上にも直結する生活リズムとして位置づけられています。
また、朝ご飯を毎日食べている家庭は92.1%にものぼるそうです。 これは、成績上位の子どもを持つ家庭に共通する習慣の一つとされていました。
まずは早寝をすること。それによって朝すっきりと起きられ、自然とお腹も空き、朝食をしっかり摂るようになるという流れがあります。
また、前述のスマホの話とも関連しますが、寝室にスマホを持ち込まないことが、生活リズムを整えるうえで非常に大切であることもあらためて感じました。
一方で、少し意外だったのが、23時頃まで起きている家庭も多いという点です。 自分の感覚では、「22時頃までには寝ないと、8時間の睡眠はとれないのでは?」と心配になるところ。
とはいえ、共通して言えるのは「毎日同じリズムを保つ」ことの大切さ。 多少の就寝時間の違いがあっても、起床時間を一定に保つ意識が、生活全体の安定、学力の向上につながっているのだと感じました。
勉強に対する「ご褒美」はアリ?──意外だった肯定的なスタンス

「勉強にご褒美なんて…」と、私自身はどちらかといえば否定的な立場でした。 だからこそ、本書において成績の良い子の家庭が“ご褒美”をどう捉えているのかは、とても興味深いテーマでした。
意外だったのは、“ご褒美”を取り入れている家庭が多いという点。 そして著者自身も、「うまく活用した方がよい」と明言していたことです。
著者によれば、長年の指導経験のなかで、ご褒美によってマイナスとなっている子を見たことがないとのことでした。
具体的に挙げられていた“ご褒美”の内容も、決して過剰なものではなく、次のようなものでした:
- 趣味の費用を援助する
- ゲーム用のカードを与える
- 現金
- 食事(外食や好物など)
とくに「食事」をご褒美にするケースについては、家族で一緒に楽しめる点が魅力的で、個人的にも好感を持ちました。 単なる報酬ではなく、家族のコミュニケーションの機会としても活用できるのが良いところだと感じます。
まとめ|ヒントが詰まった一冊
総じて、本書はとても参考になる一冊だと感じました。 目次構成もしっかりしており、最初から通して読むだけでなく、気になるテーマから読み始めても理解しやすいつくりになっています。
たとえば、あるテーマについて疑問が浮かんだときには、 その項目に直接飛んで確認するような“拾い読み”でも、十分に学びが得られると感じました。 なぜなら、本書では重要な考え方が繰り返し丁寧に語られているためです。
とくにおすすめしたいのは、
- 中学生の子どもを持つ保護者の方
- 小学校高学年で、これからの勉強習慣や親の関わり方に不安や迷いがある方
“先回りして備えたい”と感じている方にとって、多くのヒントが得られる一冊だと思います。
また、書籍を購入することでアクセスできる成績上位家庭のアンケート結果も、非常に参考になりました。 リアルな家庭の実例を知ることで、「わが家ではどうするか?」をより具体的に考えられるきっかけになります。
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。リンク先の商品を購入すると、運営者に収益が発生する場合があります。



コメント